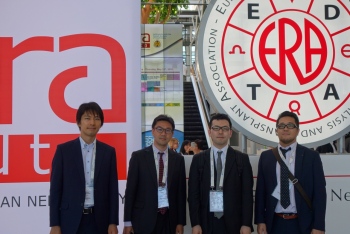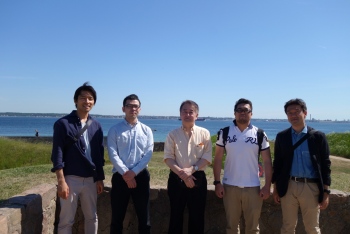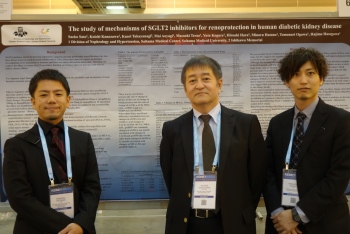カンファレンス
大学での診療にとって大切なことは「一人一人の患者さんを全員で診る」と言う点にあり、病棟でも外来でも一人一人の医師が個別に診療を行っているわけではありません。カンファレンスは「全員で診る」ために必要不可欠であり、教室にとって最優先の定例行事です。しかしカンファレンスが担当医の「報告会」になってしまっては所期の目的を達成できません。全員で意見を出し合い、時には激しい議論を戦わせ、教室として統一した方針の下診療を行うため、意見を出しやすい雰囲気作りにも留意しています。また卒前学生や研修医にとっては大切な教育の場でもあり、自らの考えを整理し、プレゼン技術を磨き、深い勉強へのきっかけを提供するものでもあります。カンファレンスにおける研修医教育を大変重視していることも当教室の特徴と言えます。
教室では種々の疾患における治療成績の見直し、検証作業を継続的に行っており、こうした解析結果を治療方針策定に生かしています。
新患、重症カンファレンス
毎週月曜の夕方から、前回のカンファレンス後にご入院になった患者さんや重症の患者さん、病態に大きな変化があった患者さんを中心に、外来患者の中で治療方針を全員で検討すべき症例などについてもカンファレンスを行っています。このカンファレンスでは研修医教育にも時間を割き、また問題点の抽出を通じて新たな研究テーマの相談なども行っています。
全症例カンファレンス
毎週木曜日の10時から12時半まで、当科入院全症例と他診療科から診療依頼を受けている症例、各自の外来での要検討症例などのカンファレンスを行っています。当科の各種のカンファレンスの中でも、最も重要なものと位置づけられています。当科が診療に関わる全ての症例の臨床情報を全員で共有し、また治療方針は全てこのカンファレンスで決定されます。
研修医は受け持ち症例のプレゼンテーションを行いますが、特に2年目初期研修医に対しては治療方針決定のプロセスへの参加を重視して指導していきます。
当教室の診療では臓器喪失である透析導入症例や、遺伝性疾患である多発性嚢胞腎、新規及び外来治療継続中である腎移植症例なども多く入院しています。こうした点に加え、社会構造の変化や症例の高齢化などが相まって、近年ではメンタル面での不調を呈する場合も多く見られます。このためカンファレンスには、この領域に精通した臨床心理士にも適宜同席して頂きアドバイスを頂いています。
血液浄化センター カンファレンス
毎週水曜日と木曜日の朝8時30分から血液浄化センター内で、血液浄化療法症例に関するカンファレンスを行っています。腎・高血圧内科医師、血液浄化センター所属の看護師、臨床工学技士が参加し、職種の垣根を越えた情報の共有と、治療内容の確認とともに問題点の話し合いを通じて、治療の質の向上と共に医療安全の確保に努めています。
教授回診
毎週木曜日の午後に教授回診が行われます。
当科では病態の把握や治療方針決定は主としてカンファレンスで行いますので、回診では、入院患者さんに「担当医だけでなく全員で診ています」という安心感を持って頂くことを重視しています。また診察を行い担当医と質疑を行うことで、データ確認に偏在しがちな現場の医師に、実際に患者さんを診ることの重要性を伝えています。さらに医学部の学生、研修医に対する教育の場としても重要と考えています。回診には業務遂行中以外の全教室員、研修医が参加しますので、様々な観点から患者さんを診る事となります。当科では扱う疾患が腎疾患に留まらず多岐に渡る事もあり、教授回診で新しい発見や新たな課題が見つかる場合も少なくありません。
抄読会・研修医発表会
毎週木曜日の朝8時から30分程度の抄読会を行っています。教授以下全教室員が毎回一人ずつ順番に、概ね1年以内に発刊された最新の原著論文の紹介を行っています。各自の臨床・基礎研究のシミュレーションの場としている他、最新の研究成果の共有にも役立っています。
また、概ね毎月最終木曜には研修医発表会を行っています。1年目の先生には与えられたテーマについてまとめを行うことで、自己の勉強のみならず、プレゼンテーションスキルの練修の場でもあります。2年目の先生には、受け持った症例の中から症例発表をして頂きます。診療を掘り下げ、症例の背景や既報について調べ、自分の診療をふりかえる場ともなります。
教室集談会(勉強会、症例検討会、学会予演、学会報告、ミニレクチャー)
木曜17時30分から医局集談会が行われます。研究に関する話題の提供やデータの紹介、臨床に関連したトピックスの紹介、学会・研究会の予演、問題症例検討などが適宜行われています。特に教室から出される学会、研究会での演題は全て予演会を行うことになっており、本番以上に徹底した討論と問題点の指摘が活発に行われます。
学会活動
国内学会、研究会
基幹学会である腎臓学会学術総会(5月)、腎臓学会東部学術大会(10月)、透析医学会総会(6月)の他、教室が主催または運営に関与している学会、研究会が多数あります。毎年80-100題の演題発表を行っています。
● 学会、全国・広域研究会
日本腎臓学会学術総会、東部学術大会
日本透析医学会総会
日本高血圧学会
日本臨床生理学会
日本アフェレーシス学会
高血圧関連疾患モデル動物学会
日本急性血液浄化学会
腎と妊娠研究会
氷川フォーラム
腎間質障害研究会
関東腎研究会
多発性嚢胞腎研究会
臨床体液研究会
トランスポーター研究会
日本腎不全栄養研究会
日本アクセス研究会
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム
日本HDF研究会
日本医工学治療学会
バスキュラーアクセスインターベンション治療研究会
日本サイコネフロロジー研究会
● 県内研究会
埼玉腎臓研究会
埼玉県高血圧研究会
埼玉臨床体液カンファレンス
埼玉アクセス研究会
腎血管カテーテル治療研究会
埼玉透析医学会
埼玉CAPD研究会
埼玉心臓・腎臓治療研究会
腎不全連携セミナー
国際学会
基幹学会であるアメリカ腎臓学会(American Society of Nephrology)、欧州腎臓学会(European Renal Association)をはじめ基礎研究、血液浄化関連の多数の国際学会に参加し、毎年10-20題程度の発表を行っています(「業績」参照)。